―これまでのご研究についてお話し下さい
私はこれまで、生命倫理の領域では主にHIV/AIDSに関心をもって研究と実践に取り組んできました。HIV/AIDSに関心をもったのと同じ時期に、生命倫理に関わり始めました。
ドイツ留学から戻ってきた1980年代前半に、自由論の観点から医療に当事者が参加するインフォームド・コンセントという考え方に関心を持ち始めたのがきっかけでした。そのとき、薬害もそうですが、エイズがまさに人権の問題として登場したのです。1986年の松本事件をご記憶でしょうか。フィリピンから出稼ぎに来ていた女性のHIV感染が判明したところ、パニックが起きたのです。その頃はバブル景気で、アジアから地方都市に労働者が来るようになり、一部はセックスワークをさせられていました。とんでもない生活環境で暮らさざるを得ず、風呂もないので銭湯に行くわけです。そうしたら、ウイルスをもっているのではないかと、銭湯が外国人の利用を断るという事態にまで発展しました。まさにHIV/AIDSは最初から人権の問題でもあったのです。その後、1987年には日本で初めての女性のAIDS患者が報道されプライバシーが侵害された神戸事件、同年にはHIV陽性の女性の妊娠・出産に社会が過剰に反応した高知事件が起こります。当時私はカント倫理学の文脈で自由の問題を考えていたので、これはどういうことなのか、HIVに感染した人たち、病気とともに生きている人たちは社会でどのように扱われてしかるべきなのか、という問題を考え始めました。これがその後、私の生命倫理研究の方向を決めることになりました。そのなかで、1994年に横浜で開催された第10回国際エイズ会議に関わることになりました。
―国際エイズ会議とはどのような会議ですか
横浜会議のときの国際エイズ学会の会長は、のちに『ノー・タイム・トゥ・ルーズ』『エイズは終わっていない』を書いたピーター・ピオットでした。当時、ピオットは若い医学研究者でベルギーからWHOに出向していました。国際エイズ会議には通常の医学系の会議とは異なる特徴があります。医療者、医学をはじめ多様な学問的バックグラウンドをもつ研究者、行政、ここまでは同じですが、さらにHIV陽性者とキーポピュレーションの参加が不可欠なのです。HIVの影響をもっとも受ける人たち、その対応への要となる人たち、セックスワーカー、薬物使用者、男性同性愛者などです。
当時、日本で事務局を担当したのは厚生省で、初めは医学者の会議が意図されていました。しかし、そもそも当事者がいないとエイズの国際会議になりません。当初は軋轢もありましたが、次第に厚生省のなかにも理解者が出てきました。お互いやっていくうちにすこしずつ理解が進み、当事者とコミュニティの参加、そして人権への配慮が生まれてきたという経験をしました。
横浜会議の時点ではAIDSはまだ不治の病でした。会議が終わるとき、陽性者がお互い次にはもう会えないかもしれないと別れを惜しみ、抱き合っていたのが印象的でした。
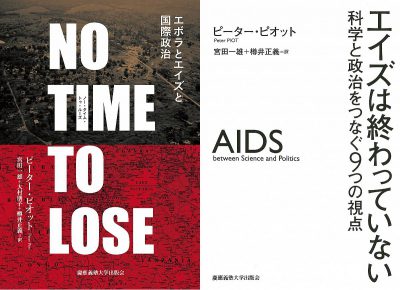
―治療法の開発とその後の変化について教えて下さい
1996年にバンクーバーで開かれた第11回国際エイズ会議の標語は「One World, One Hope」、世界中が治療という共通の願いを共有していました。そしてこの会議で、前年に開発された治療法のお披露目が行われました。治療法の登場は大きな福音ではありましたが、これよって皮肉にも世界は一つではなくなり、HIV/AIDSは南北問題に変わりました。裕福な国の人も、貧しい国の人も、皆等しく死を避けられなかったのが、貧富によって死ぬ人と生きられる人とが分けられたのです。
途上国における治療の普及、健康権の擁護は重大で緊急の課題として残されていますが、先進国での治療は大きく前進しました。しかしより広い人権の観点からは、先進国でも変化は緩慢です。HIVから社会はなにを学んだのかと、ときに思わざるを得ません。HIV以降も、SARS、鳥インフルエンザ、エボラ、そして今は新型コロナウイルスです。病原体に対処するというより、感染者、あるいは疑われる人を排除すればよいという方針では、予防を含めて感染症の問題は解決しません。感染している人、感染の疑いがある人、対策の影響を強く受ける人、そうした人たちに配慮し、人を人として扱うことが、人権の上からも、公衆衛生のためにも求められる、それがHIVから世界が学んだことです。
―現在のご研究、ご活動についてお話し下さい
現在はHIVから薬物使用の問題にも関心をもっています。薬物注射だけでなく、薬物使用によりセックスでの感染予防がおろそかなることも、感染を拡げているからです。薬物依存は疾患であり、背景にメンタルヘルスがあり、薬物使用は健康問題なのですが、私たちの社会ではもっぱら刑事問題と見られ、薬物使用者は犯罪者として排除され孤立させられています。
また同じくキーポピュレーションである性的少数者にも、家族や友人のなかで生きづらさを感じている人がいます。そうした人たちが話をできる場、繋がれる場をつくること、ソーシャルインクルージョンを進めることが、予防と治療を進めるうえでも重要だと考えています。
―日本生命倫理学会の思い出をお聞かせください
中谷瑾子さんが大会長をなさって、1995年の第7回年次大会が慶應義塾大学で開かれ、それを通じて、以前からお世話になっていた同学の先達、坂本百大さん、飯田亘之さん、加藤尚武さんだけでなく、多くの研究者と出会うことができました。中谷さんは法学部、私は文学部にいたわけですが、三田キャンパスではほぼ全教員の研究室が一つの建物に入っていて、小さいがまとまっているという良さがあり、中谷さんには拙稿に意見をいただいたり、ご自身の研究会に呼んでいただいたりと、学ぶ機会をいただきました。
―生命倫理学会への希望、若い研究者のみなさんにエールをお願いします
私が生命倫理に関わり始めた三十数年前、当時は「生命倫理学者」などいませんでした。哲学、法学、医学、看護学など、各自が専門領域をもっていて、それが協同するという、まさに生命倫理はインターディシプリナリーな取り組みでした。だんだんと生命倫理を専門にする人が増えてきましたが、一つのディシプリンから具体的な問題へ―個人のなかではその逆も―というのが、その頃の生命倫理学の特徴です。それは医療の問題を多角的に眺めるという意味で、よいことだと思っています。
幸運だったのは、当事者や医療者と一緒に仕事ができたことです。医療の素人にとって、彼らとどれだけ情報共有できるかで、生命倫理研究の質が決まってくると思います。生命倫理には、木村利人さんがおっしゃるように、市民運動という側面がありますが、当事者とのそうした運動に、NGOでの活動を通して関わることができました。また学生時代からの繋がりもあって、遠慮なしに話し合える医療者が常にまわりにいたことも、私にとってはありがたいことでした。さらに医療者の中にも本気で哲学や倫理学に取り組もうとしている人もいます。そういう人たちと腹を割ってつきあって行くことで、研究者として開ける世界が変わってくると思います。

樽井正義
慶應義塾大学名誉教授、国際医療福祉大学成田看護学部教授。慶應義塾大学大学院修了後、1976年より慶應義塾大学文学部助手、専任講師、助教授を経て1996年より教授。哲学倫理学を専攻し、感染症が共同体と国際社会に提起する倫理問題をテーマに研究。国際エイズ学会(IAS)会員でアジア太平洋エイズ学会(ASAP)元副会長。NPOのエイズ&ソサエティ研究会議、ぷれいす東京、エイズワクチン開発協会でそれぞれ理事を務めている。
[代表的な著作]
- 『ハームリダクションとは何か』共著, 中外医学社, 2017.
- 『ヘルスリサーチの方法論』共著, 放送大学教育振興会, 2013.
- 『ヒューマニズム薬学入門』共著, 培風館, 2012.
- 『カント哲学案内』共著, カント全集別, 岩波書店, 2006.
- ピオット, P., 『エイズは終わっていない―科学と政治をつなぐ9つの視点』共訳, 慶應義塾大学出版会, 2019.
- ピオット, P., 『ノー・タイム・トゥ・ルーズ―エボラとエイズと国際政治』共訳, 慶應義塾大学出版会, 2015.
- ハステッド, G.L., ハステッド, J.H., 『臨床実践のための看護倫理』共監訳, 医学書院, 2009.
