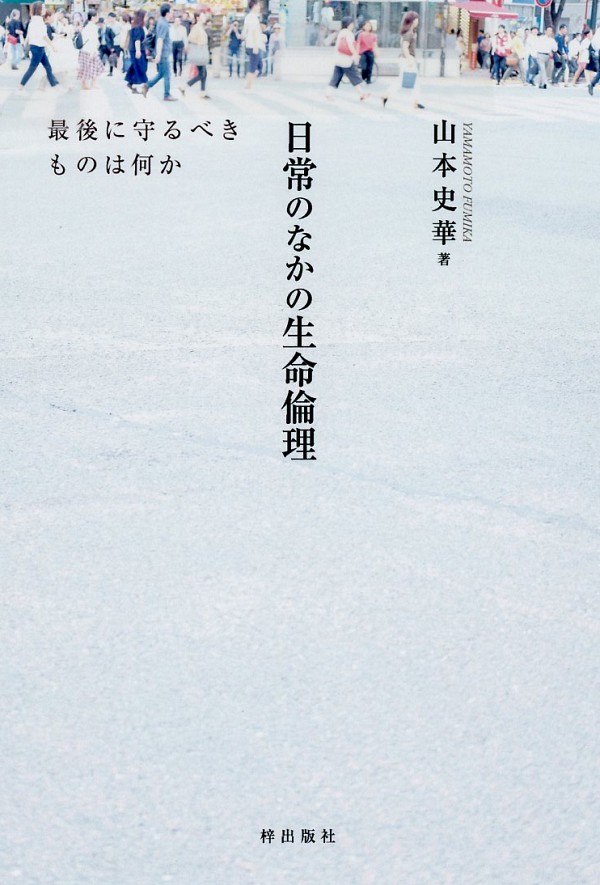生命倫理学の課題にも流行り廃りはあるだろうが、たとえ流行っても廃ってはいけないものがあるのではないか。かつて日本で、脳死臓器移植は、様々な分野の論客を巻き込み、丁々発止の議論が交わされたが、近年、その話題はほとんど報道されなくなった。学会においても、あたかも議論は尽くされたかのように、脳死臓器移植を主題とする発表はまず見かけない。だからといって脳死臓器移植がなくったわけではない。それは日常的に行われている。課題は日常のなかに溶け込んでしまうと、どうも見えにくくなるようだ。しかし、見えにくくなることは、課題が終わることを意味しない。むしろ、見えにくいものを捉え、言説化することが研究者には求められているように思われる。
哲学・倫理学畑出身の私は、生命倫理学とかかわる中で、医療現場の速度についていけないと感じることがよくある。医学や医療の速度は凄まじく、それに応ずるための倫理や倫理学が必要なことは確かだ。だが一方で倫理学は、同じ地点で足踏みするかのように、生や死を二千年以上の間、執拗なまでに問い続けてきた学問でもあり、速さには無縁の側面がある。さらに言うと、倫理学は、眼に見えないもの、見えにくいものを積極的に主題としてきた。魂や心、善や悪、自由や意志などは言うに及ばず、死だって、厳密に言えば眼に見えやしない。我々に見えるものは、しょせん死体に過ぎないからだ。
本書は、日頃ほとんど医学や医療と無縁な大学生を念頭におきながら、彼ら彼女らに生命倫理学の課題について関心を持ち続けてもらえるようにとの思いから、書きおろされた。大仰な言い方を許してもらえるのならば、タイトルにつけた「日常のなかの」という言葉には、見えにくくなっている生命倫理学の課題を、加速する医学や医療とは一定の距離をおきながら問い直したいという意図が込められている。その意図の実現に成功したかどうかは甚だ心許ないが、私が念頭においた学生たちのように、普段は医学や医療と関係のない人にこそ読んでもらいたい。
医学や医療は日常の価値観や規範観を知らず知らずのうちに変容させていく。そのような緩やかな変化を察知し、それを可視化し、生や死の倫理を問い直すという作業は、まるでシジフォスの岩のように、生命倫理学の研究者に課せられた、廃れてはならない課題なのではないか。なぜなら我々は、たとえ医学や医療から離れられても、生命からは離れられないのであり、その生命の在り方を問題にすることが倫理学本来の課題だと思うからである。