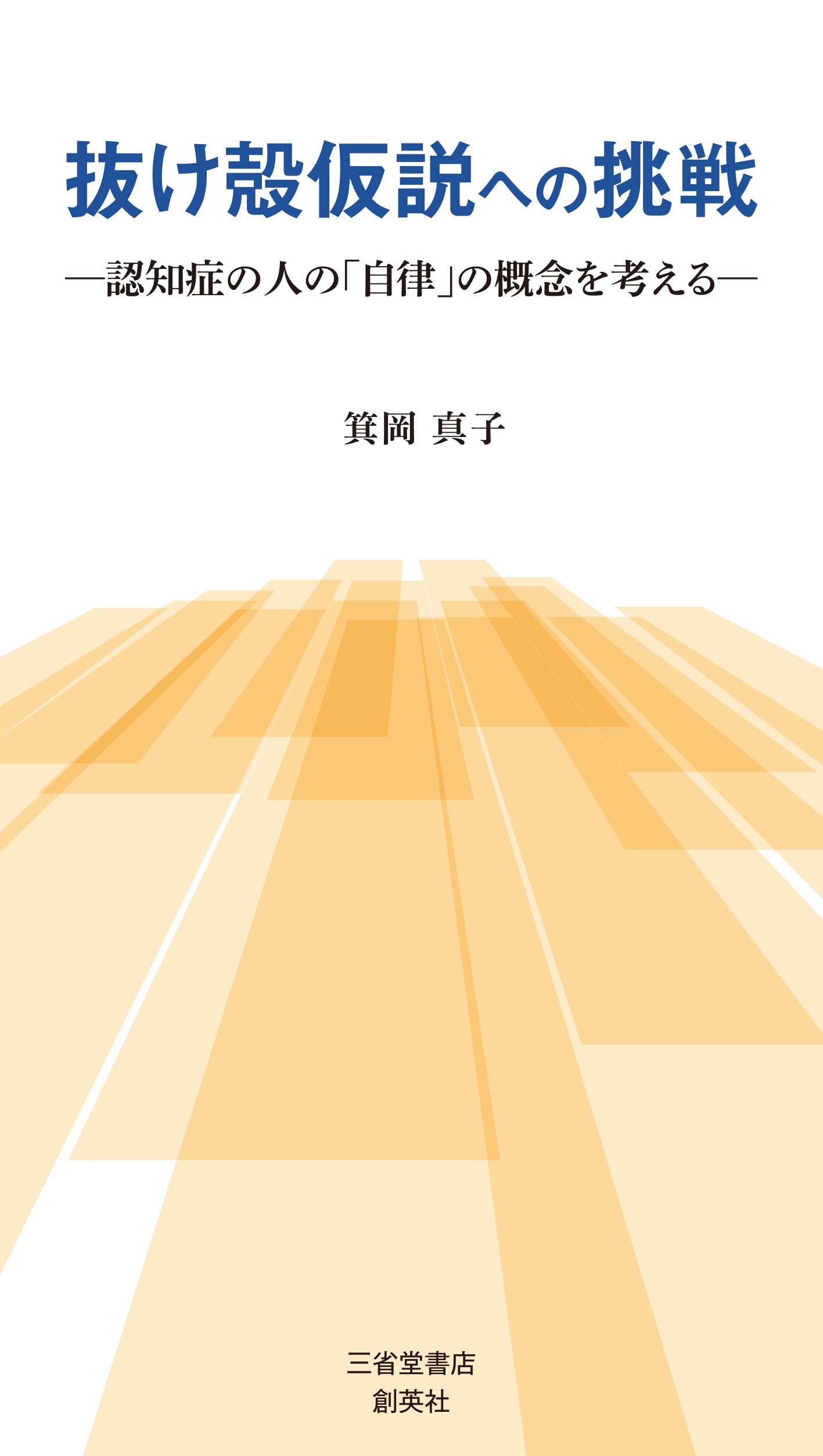【概要】
認知症になると抜け殻になってしまい、自分では決められないのか―「自律」は自己決定と結びつき、現代の医療現場の意思決定の中心的価値である。本書は、自律の持つ「正」と「負」について論じ、自律を一旦解体し、その後、自律を統合する再概念化に挑んでいる。そして、自律の概念には“ゆらぎ”があることを指摘し、これまで社会が自明としてきた排除のためのボーダー(線引き)を、「インクルーシブ」(包み込む)にするためにはどうすればいいのかを問うている。(内容詳細は稲葉氏による「刊行に寄せて」を参照)
箕岡 真子(箕岡医院)
【抜け殻仮説への挑戦・刊行に寄せて】
内科医で臨床倫理の理論家の箕岡さん(著者)と、法律家で臨床倫理の実践家の私は、大学・学会等を通じて、数十年お互い知的刺激を与え合ってきた。著者は、あの時の対話・会議で、確かに私も「直感」したテーマや問題意識をしっかりと温め、事前指示、認知症、看取りなどの「自律」に関わる著書を書き、長い年月の準備の上で、今、咲くかのようにその成果を本書に込めたものと分かる。著者の臨床倫理は、自律との格闘の歴史である。
本書の主題は、自律の持つ「正」と「負」についての書であると読み解く。自律は自己決定と結びつき、現代の中心的な価値を表している(「正」)。しかし、自律は、「誰が自律的か」という資格を問う。意思決定能力である。この能力があれば、説明を受けた人の自発的な意思は尊重される。しかし、もしなければ、家族が(本人の意思を推定しながら)決めていくというルールに流れる(多くの医療系のガイドライン等)。しかし、これでは、認知症の多くの人が「自律的でない」と判断され、自律が認められないことになる。これは、現代自律論が差別をしているということに外ならない(「負」)。この線引きの向こう側にある認知症の人にも自律の恩恵を及ぼすために、本書は、自律を一旦解体し、その後、自律を統合する。認知症の人に多く向き合い、医療等の現場で、認知症の人の持つ可能性・可変性・可塑性を実感した内科医の筆の運びは実に説得力がある。
Autonomy の訳語である自律は、自立と間違われる(特に介護の領域で)。つまり、自律の概念を理解することは難しい。本書では、杉山さん一家の日常の物語を書くことで読者に、自律を尊重することは、決して終末期や人生の最終段階だけではない「身近な生活」にある問題だと語りかける(第1章)。杉山さん一家の問題は、展開し、その後、清三郎さんは、「認知症」が進行し、「胃ろう」の導入が検討される。避けることができない人生の最終段階の問題である。ここでは、認知症を始めとする意思決定能力が低下した人にも意思決定に参加してもらうことの重要性が説かれる(第 2 章)。
第3章は、新しい認知症ケアの倫理が語られる。我々が多くのバイアスのかかった考えに染まっていることに気づくプロセスである。第4章は、「4章が、実は本書の中核となります。これまでの1章から3章までは、4章を理解していただくための基礎知識」で始まり、著者の中心的な主張である。
著者は、「人格を尊重することは、その人を自律的主体として認めること」という考えは間違いではないが、「自律的でない人には人格はない」という考えは間違っていると、厳しく指摘する。新しい認知症ケアの倫理の役割は、「自律の低下した弱い立場の人々を排除するのではなく、包み込むこと」と宣言する。更に、「人が、自分のために決める場合」と「他人のために決める場合」との違いを指摘し、医療の現場で行われている「意思決定能力があれば自己決定、なければ代理判断」という考えや、人生の最終段階の医療・ケアの決定のプロセスに関するガイドラインのいう、「本人意思が確認できる場合」の自己決定と「確認できない場合」の代理判断のプロセスという考えに、異なった考えを示す。ここでは、著者の近代の自律概念に対する幅広い、しかも奥深い見方への理解が、バックボーンとなっていることを、注意深い読者は感じ取るであろう。
その上で著者は、自律を「とどまったもの」としてではなく、自律には「ゆらぎ」がある、 つまり変わりゆく、あるいは関係性により変わり得るものであると指摘する。認知症の人や脆弱な人(vulnerable)の自律にはゆらぎがあり、「ボーダーライン」上の「グレーゾーン」の人がいる。そのような人の自律を尊重するには、どうすればいいのかと問いかける。それができなければ、「自律の低下した弱い立場の人々を排除するのではなく、包み込むこと」 という新しい認知症ケアの倫理は実現できない。このように、人は高齢者になっても、また、 認知症になっても、その時とその場にふさわしい花を咲かせることができるものであると いう、著者の人間の可能性への信頼が随所に感じ取られる。その後著者が提案する方策は本書をじっくりと読んでみて欲しい。
本書は一般の読者に届くように、分かりやすく書かれているが、世界・日本の臨床倫理の歴史がしっかりと記述され、また、倫理の基本的な考え方も説明されており、医療者・介護者、更に臨床倫理実践者にも、適切である。
今、障害のある方、性的マイノリティーの方を含め、これまで社会が自明としてきた排除のためのボーダー(線引き)を、「インクルーシブ」(包み込む)にするためにはどうすればいいのかが問われている。自律という観点からこれまで排除されてきた認知症の人を包み込むことを意図する本書は、このような政治哲学にもつながる。
稲葉 一人(弁護士・元判事・元検事)