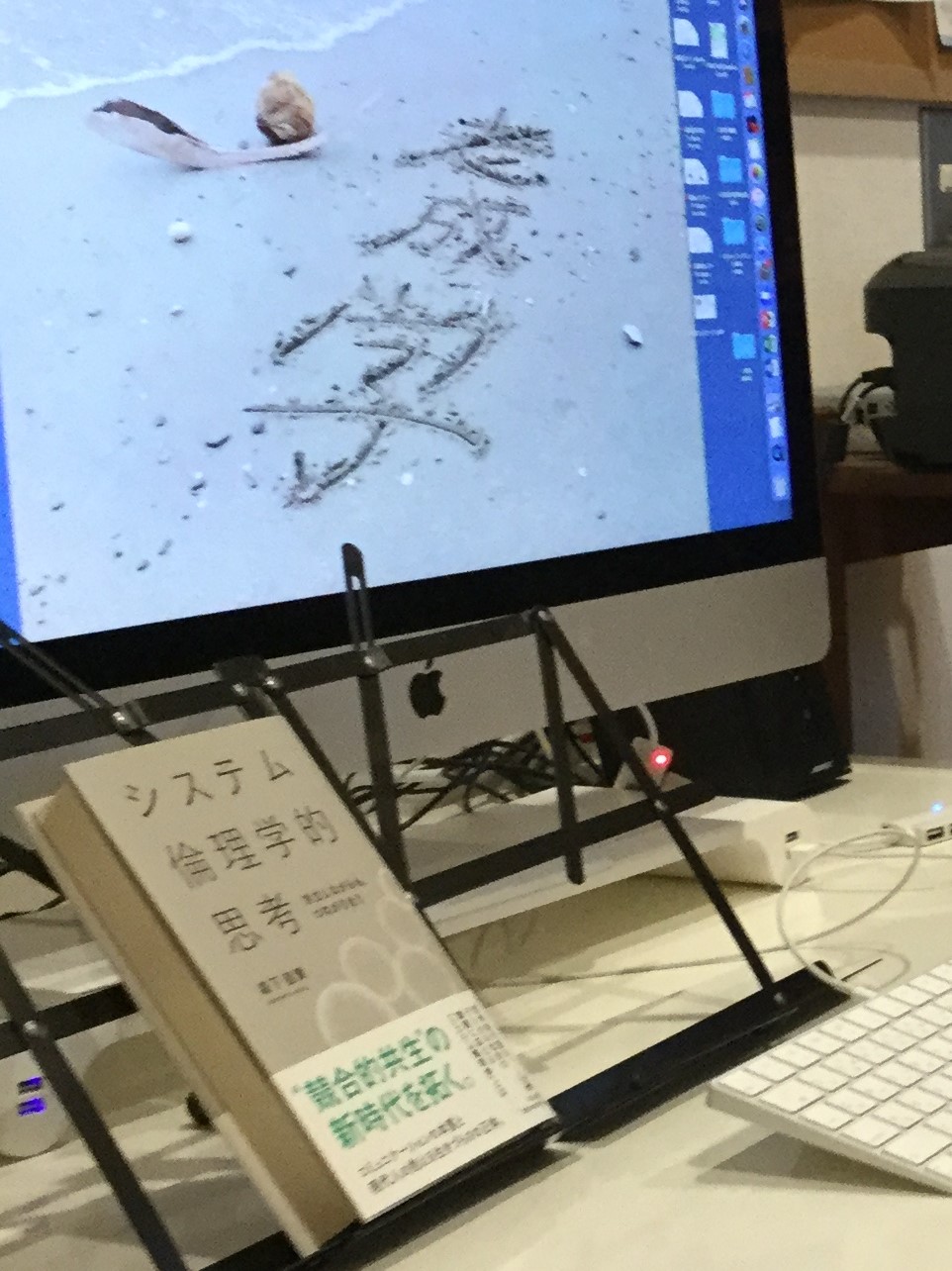日本生命倫理学会公式ホームページでは、「研究室訪問」というコーナーを新たに設けました。このコーナーでは、本学会会員の皆様が所属する研究室・研究センターを本学会情報委員会のメンバーが訪問し、研究室・研究センターの紹介に加え、どのような研究に携わっていらっしゃるのか、これからどのような研究が必要か、といったことについて、ざっくばらんにお話を伺います。学際的で多様な分野の研究者の方々にお話を伺うことで、皆様の研究活動にプラスになれば幸いです。伺った内容は、何枚かの写真とともに情報委員会のメンバーが執筆した記事として本コーナーで紹介いたします。
第1回目は、老成学研究所の森下直貴先生の研究室を紹介します。2020年6月25日、浜松市内の老成学研究所にてお話を伺いました。

老成学研究所の入口にて
森下先生は現在、20年前に翻訳を含めて出された『「生きるに値しない命」とは誰のことか―ナチス安楽死思想の原典を読む』(窓社、2001年)の新版の出版に向けて取り組んでおられます(中公選書、2020年9月刊行予定)。
インタビューのちょうど前日に、新版のエピローグを書き上げられたとのことでした。「クラクフ/アウシュビッツ訪問記」と題されたこのエピローグには、反ナチスの拠点だったヤギェヴォ大学の奥まった建物の中庭に、20名の教授たちの顔写真を見つけたというエピソードがあります。顔写真パネルの横には、大学教授会の最中に、反ナチスだった183名の教授が連行され、アウシュビッツに送られたと記されていたそうです。「教授会に出ていたから逮捕されたのかと。だったら、教授会を休んでいた人はどうだったんだろうと思ったわけですよ。よく読んだら、そういう人も後で逮捕されたとあったので、教授会には出ても出なくても同じなんだなと思ったりして」と冗談めかして仰いました。
「この本に収められた翻訳部分は、ナチスの安楽死政策との関係というより、もっと深いところで命の選別を論じている総合理論です。そのように位置付けて、それにどう対峙するのかという形で本を書いています」
「能力差別、つまり社会集団にとって役に立つ・役に立たないということの意味を問い返す必要があります。相模原の事件でも、未然にどうして防げなかったのか。植松という人の疑問に対して周囲の人たちは誰もちゃんと向き合って答えていません。逃げていますよね。本人は否定されていないので、みな心の中では賛成しているのかな、と思ってしまった。答えた人がいたとしてもどうだったかわかりませんが、議論の厚みがなかったのかなという反省があります」
相模原事件の植松被告が抱いた疑問に誰も正面から答えてこなかったこと、橋田壽賀子『安楽死で死なせて下さい』に代表されるような、生きる意欲がなくなった高齢者の安楽死を遂げたいという希望に一定の共感者がいること、現在のパンデミックにおけるトリアージの中で命の選別がとり沙汰されたこと、といった問題群を背景に、20年前とは違った形で、改めて生命の価値をめぐる議論――役に立つか立たないかで分類しようとする思考法――を「システム倫理学」の観点から問い直す必要がある、という見地から、新版の出版に踏み切られたそうです。
森下先生の造られた「システム倫理学」の「システム」とはコミュニケーションのシステムのことで、日常生活の言葉でいいかえると、「システム倫理学」は「つながり合いの倫理学」となります。詳細は『システム倫理学的思考』(幻冬舎、2020年)において示されていますが、この「システム倫理学」を理論的基礎として、研究所の名前でもある「老成学」が成り立っています。
この老成学の領域については、鶴若麻理さんとの共著で「日本における最晩年期高齢者の<生き方>の一側面―「新老人の会」の調査を踏まえて」『生存科学』30(2), 69-90, 2020をお示し頂きました。
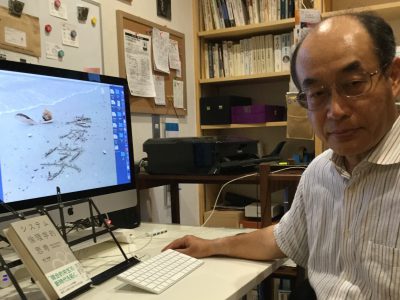
老成学研究所でお話を伺う
「今まで80歳、85歳以上の方たちの研究って、質的研究はありましたけれど、量的研究ってなかったんですよ。日野原先生がご存命のうちにと思って新老人の会で調査させて頂いたんです。私の四次元相関の枠組みを使ってアンケート項目を作ったり、分析もしてみました」
「いま主に、老いを中心に人間の生き方・死に方を考えています。人生の老いという段階において、老いの深まりに応じていろいろな生き方があり得る。それを丁寧にモデル化していきたい」
お話を伺っている中で、この本読まれたことありますか?と、ボーヴォワールの『老い』をお示し頂きました。彼女が62歳の時に発表した『老い』で示されているのが、現在の表現ではアクティブ・エイジングであること、78歳で亡くなったボーヴォワールが、もし80代、90代まで生きていたら、また違ったことを考えていたはずで、そこが知りたかった、と仰いました。
「死に方は老い方全体の中にある。問われているのは生き方で、そこでの焦点は、当事者の生きる意欲の問題です。だとすれば、安楽死の是非をめぐる正当化の議論とは違う形の生命倫理学が必要になります。私のコミュニケーション理論では、意味をどう解釈するかのやりとりが人間のコミュニケーションの特徴であると考えます。老人同士でも、医師と患者でも、コミュニケーションがあるということは、一方がいて、他方がいて、役割があるわけです。それぞれ一定の役割を持ちながらコミュニケーションをしています。役に立つ・役に立たないをコミュニケーションにおける役割ととらえたときに、認知症であろうが、障がいをもっていようが、当然、コミュニケーションを担っているわけです。そこで見事に生きてみせる、老いてみせる、死んでみせるという形の問題の立て方をすると、『老人になって生きている意味がありません、なぜなら役に立たないんですから』という言い方に対して、どんな状態になっても、人が老いて死んでいくさまを、若い人が見て、感じたり学んだりできるとすれば、最期までコミュニケーションの役割を果たすのも生き方ではないか、と言えるはずです。生き甲斐がないと死を選んでしまうというのは、つながりの点からみると、もったいないですね。」

それぞれのご著書の位置づけと流れをとてもわかりやすくお話し下さいました
順序だててお話を伺っていくと、「老い」というテーマに対する森下先生の取り組みが、広義の安楽死についての森下先生の問題意識と極めて密接にリンクしていることがとてもリアルに納得できました。森下先生はさらに次のようにもおっしゃいました。
「安楽死をとりあげ、老人の老いの最終局面の方から話をしていますけれど、もう少し広げて、さまざまな分野の思考法を私の枠組みで整理しながら、いろいろな人たちと研究を進めたいなと思っているんですよ」
「さまざまな分野」には、医療や福祉の領域だけでなく、数学や物理学など、生命倫理学領域からは一見遠く思われる領域も含まれています。森下先生は、老成学研究所のホームページに吉田武『虚数の情緒―中学生からの全方位独学法』(東海大学出版会、2000)の書評を掲載しておられます。
「物理学や生物学の人たちの考える『システム』と、人文社会学でいう『システム』の交流が全然ないんですよ。文理融合の場所を私のホームページで提供して、ちょっと広げて行こうかなと思っているのです」「コミュニケーションシステムの理論的な研究と、生命倫理などの応用研究の両方をやっていて、その中軸にあるのが老成学です。ここから両極を見据えて研究を展開したいなと思っています」
(情報委員会 加藤太喜子)