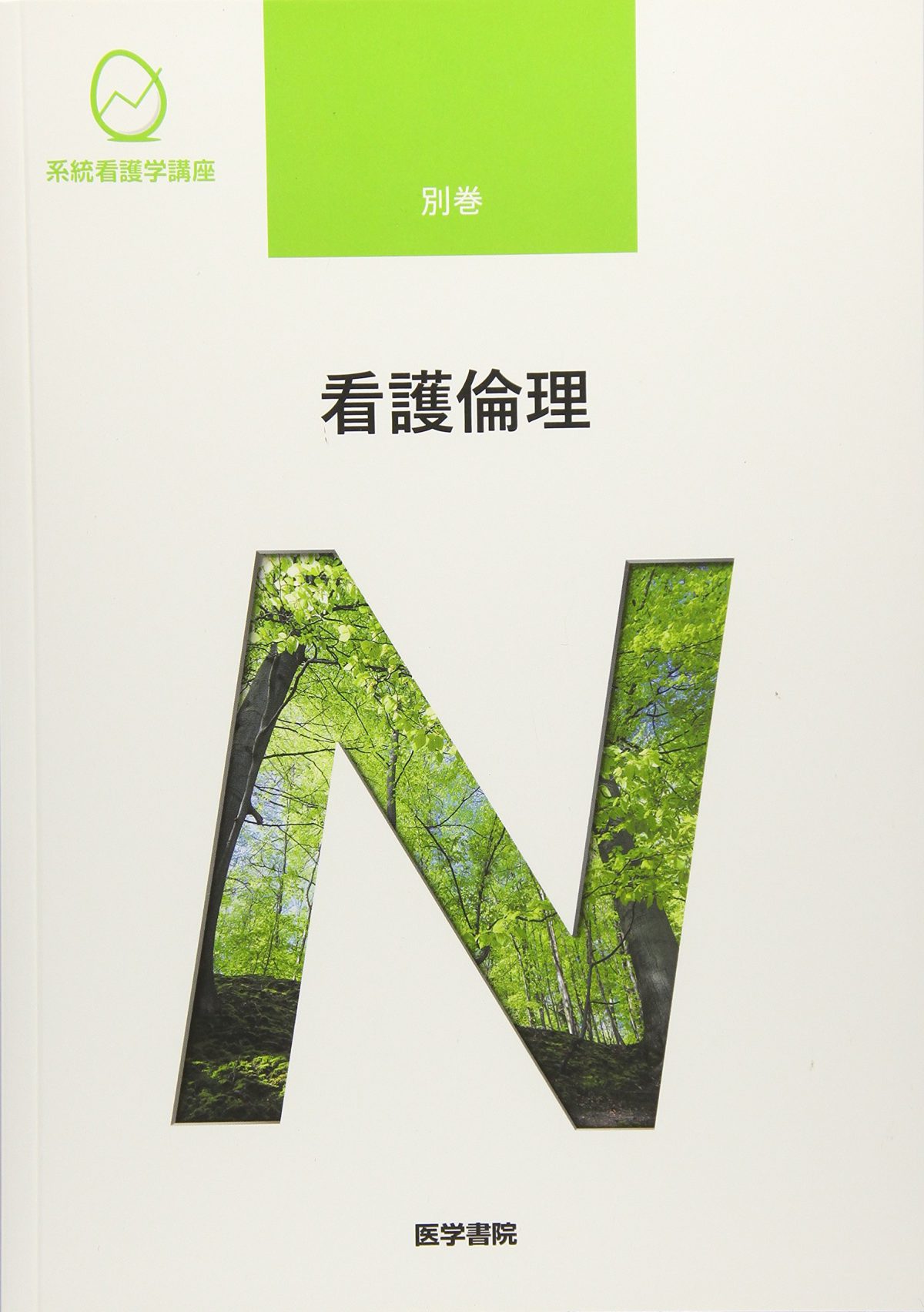筆者は医療資格を持っていない。そのような人間が、医療従事者になる人たちが使う倫理の教科書を書くというのは、どういう意味をもつのだろうか。本書の執筆を出版社の医学書院から依頼されたとき、そのようなことを考えた。実は、これと同じことを、2005年に同じ出版社から『医療倫理学の方法』を出したときにも考えた。あのときに自分なりに得た結論は、「医療」という日本語を、英語のhealthcareのような広い意味に捉え直してみてはどうか、というものだった。healthcareは、特定の職種(例えば医師)の専有物ではなく、歯科医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、歯科衛生士(以上が筆者の大学で育成している医師以外の医療職であった)や、もっと広い範囲の職種に共有されるべきものだろう。もっと言えば、healthcareは、医療資格を持つ専門家の専有物でもなく、患者の側の人間、あるいは、資格があろうとなかろうと、他者の健康を気遣い、ケアしようとする者すべてのものであるはずだ——。
医療現場の倫理問題をどう扱うべきかと聞かれれば、様々な職種が連携して、患者や家族などと対話をしながら考えていくのがよいだろうと、多くの人が思うはずである。しかし、医療従事者には自分たちの業(プロフェッションとしての業であり、経済的な利益を生みだしていく業でもある)としての医療を運営していく自負と責任がある。医療従事者は、職種ごとにプロフェッションとしての自律性(他から介入されずに業をなす権限)についてのかなり強い信念を共有しているため、倫理問題を考える「場」の設定をどうするかが大きな問題になる。最近では病院に臨床倫理委員会のようなものが作られているが、その構成員の設定をどうするべきか。医療従事者の養成課程に倫理学者のような「外部者」を参画させるべきか(医師なら医師が、看護師なら看護師が、というように、当該資格を持つ者が教育を行うことが望ましいというのが、医療プロフェッションの自律性を保つために維持されてきた価値観である)。
幸いに、看護の世界では、外部者に対して受容的で、自分たちが学ぼうという意識が高い。少なくとも筆者はずっとそう感じて働いてきた。筆者が本格的に看護倫理を教えているのは、主に大学院なのだが、そこでは専門看護師などのより専門性の高い資格を得るのに、看護倫理が必修に指定されている。看護師の資格を持つ教員と、筆者のような無資格ながら医療倫理や生命倫理に通じている教員とが、どう連携しているかというと、おおむね半分ずつのボリュームで講義を分担している。筆者が最初の半分を受け持って、医療倫理の歴史や方法論を講義して、後半を看護の各分野の教員が、自分の分野で生じている倫理的問題について講義をする。面白いのは、臨床事例の検討でも、同じような図式が生じることである。有資格者は現場の問題を提示して、自分たちが何に困っているかを提示する。筆者のような人間は、それを理論や他事例との比較によって論点整理してみせる。このような図式が、教育の現場でも、臨床倫理委員会のような場でもしばしば生じる。内部者と外部者とが視点を交換するようなこの図式が、医療倫理には必要なのだろう。この図式は緊張関係にもなり得るが、うまくいけば対話的なものになる。このような方針で、筆者はこの本の自分の担当する部分を執筆した。
本書を執筆するにあたって、「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」、「看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン」、「看護学教育モデル・コア・カリキュラム」などを参照し、編集者を通じて学校関係者からの声を聞き取ったりもした。そうやって盛り込むべき事項を検討し、教室で使いやすいように、ケーススタディやグループワーク、ゼミナールなどを設けている。本書の構成などの詳細は、出版社のウェブサイトで見ることができる。出版社によれば、本書はとても多くの学校で使われているらしい。