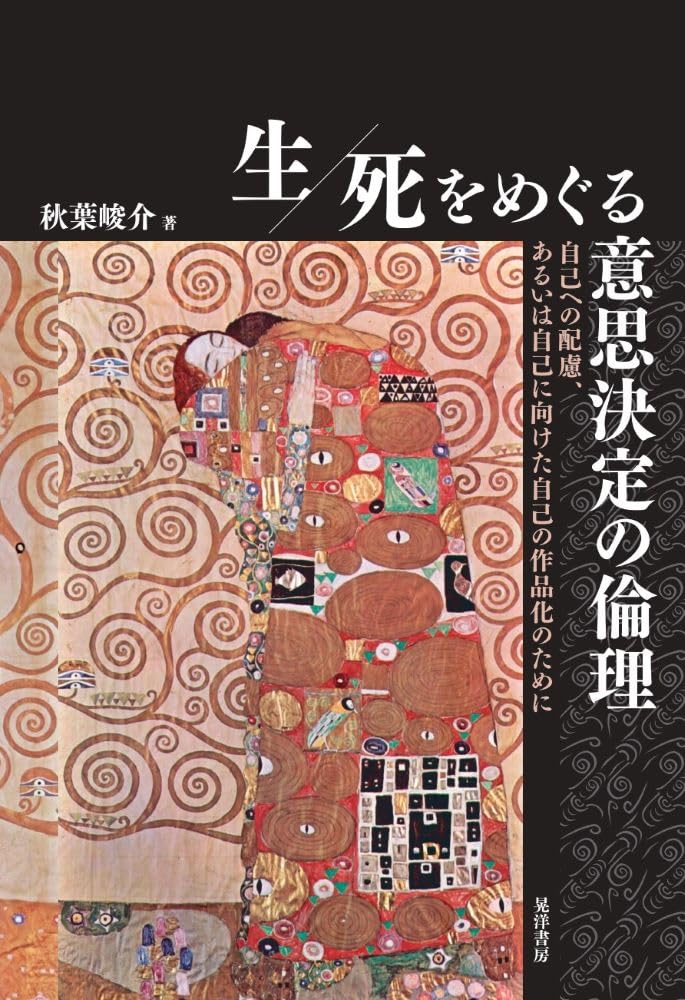本書は、「人生の最終段階」における医療・ケアに関する理論的枠組みを検討することを通じて、〈生/死をめぐる意思決定の倫理〉を批判的に再構成することを目的として書かれた博士論文(立命館大学・先端学術総合研究科)を書籍化したものです。
内容としてはタイトルのとおり、生/死をめぐる意思決定に関する「倫理」について、インフォームド・コンセント(IC)の登場から今日のアドバンス・ケア・プランニング(ACP)や共同意思決定(の推奨)に至るまでの議論の整理・分析と、その背景や内実について(批判的に)検討したものです。医療・ケアの現場における意思決定の議論・実践をめぐる倫理的・道徳的・制度的な総まとめを経て、その核心とは、たんに医療・ケアのみをめぐる議論あるいは「問題」ではないはずだ、という批判を展開することによって「倫理」を問い直す/再構成につなげるように構成されています。今日の議論・実践において重視され、きわめて重要な位置を占める「人生の物語り」や「関係性」や「家族」などをあらためて捉えなおすことで、われわれが生/死をめぐる意思決定を通じていったいなにを為しているのかを徹底的に問う1冊です。
医療やケアの意思決定に関する倫理規範や各種ガイドライン等についても取り上げて分析・考察を加えており、また、模擬事例を用いた検討も取り入れていますので、学術的な場面だけでなく、臨床の場面での応用や、「生命倫理」をめぐる見方・考え方の参考書的にも「使える」場面があろうかと思っております。また、当然、読者の立場や背景が違えば見え方も違ってくると思いますので、本書で展開される批判的検討に対して、さらにメタ的・批判的に読んでいただけると、今後この領域での議論がさらに深まるのではないかなと考えています。
研究者のみなさんだけでなく、ぜひご医療やケアの実践に携わるみなさんにも手に取っていただけると幸いです。
【小泉義之・立命館大学名誉教授による推薦文】
医療・ケアの場で、新しい死生術、すなわち、「人生の最終段階」における「人生の物語り」によるACP・共同意思決定がなされている。IC・自己決定の限界を超えて、生/死をめぐる倫理は変遷してきた。そこにケア倫理やフェミニズムも関与し、関係性や親密性としての(拡張)家族が顕在化してきた。その次第を批判的に検討し、多くの人間によって現に生きられ/死なれる倫理を、「つながっていない」者さえも生きる/死ぬ倫理を、分析して構成する初めての書である。
目次
序章
第Ⅰ部 意思決定に関する議論の変遷と家族の位置
第1章 インフォームド・コンセント
第2章 インフォームド・コンセントの限界を超えて
第3章 共同意思決定と自律・自己決定論
第4章 背景としてのケア倫理、フェミニズムと家族、ケア
第Ⅱ部 生/死をめぐる意思決定の倫理
第5章 ケア倫理の批判的検討
第6章 わたしたちはなにかを決めているのか
終章 生/死をめぐる意思決定の倫理再考
あとがき
文献
出版社による紹介ページ:https://www.koyoshobo.co.jp/book/b650479.html
情報提供: 秋葉 峻介(山梨大学)